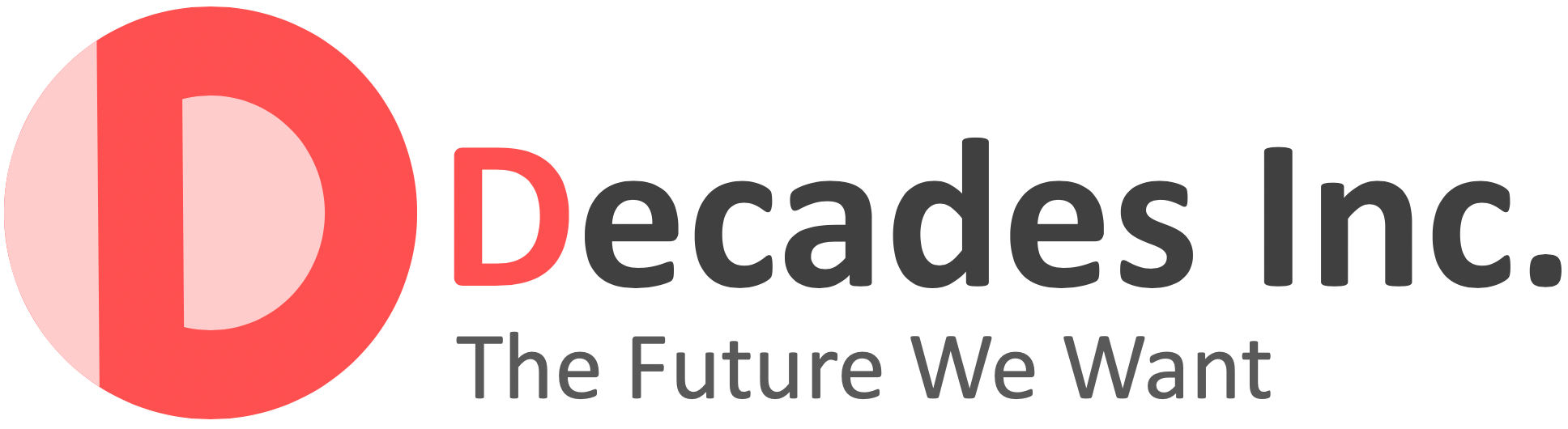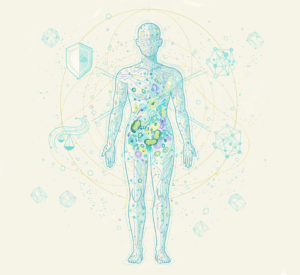花粉症の季節に悩まされる方、特定の食べ物で蕁麻疹(じんましん)や息苦しさを経験したことがある方、あるいはご家族にアレルギー体質の方がいらっしゃるかもしれません。
近年の全国調査(JAPOC2019)で、アレルギー性鼻炎の有病率は49.2%に達しました (Okamoto et al. 2020)。厚生労働省は、「国民の約二人に一人が何らかのアレルギー疾患に罹患している」と指摘しています(厚生労働省 2022; 厚生労働科学研究 2022)。アレルギーはまさに「国民病」と言えます。
しかし、ここで一つの素朴な疑問が浮かびます。なぜ、スギ花粉、ダニ、卵、牛乳といった、本来は私たちの身体にとって「無害」であるはずのものに対して、免疫システムはこれほどまでに激しい攻撃を仕掛け、くしゃみ、鼻水、かゆみ、呼吸困難といった不快な症状を引き起こすのでしょうか?
この記事では、科学とデータに基づいた視点から、アレルギーが起こる基本的メカニズム(特に「I型アレルギー」)を構造的に解き明かします。
自らの身体で何が起こっているのかを本質的に理解することは、溢れる情報に惑わされず、ご自身の健康に関する意思決定の質を高めるための「知的武装」となります。なぜその薬が効くのか、なぜ治療に時間がかかるのか、その論理的な背景を探る旅に、ご一緒しましょう。
アレルギーとは「免疫システムの過剰防衛」である
私たちの身体には、ウイルスや細菌、あるいは寄生虫といった「外部からの侵入者(病原体)」を見つけ出し、攻撃・排除することで身体を守る、非常に精巧な防衛システムが備わっています。これが「免疫」です。
免疫は、いわば体内の「警察」や「軍隊」のようなものです。普段はパトロールをしながら、「自分自身の正常な細胞(味方)」と「危険な侵入者(敵)」を正確に見分け、敵だけを攻撃してくれています。このおかげで、私たちは健康を保つことができます。
ところが、この優秀な免疫システムが、時として「とんでもない勘違い」を起こしてしまうことがあります。それがアレルギーです。
アレルギーとは、この免疫システムが、本来であれば攻撃する必要のない、身体に無害な物質(例えば、スギ花粉、ダニのフン、卵、牛乳など)を、「危険な敵だ!」と誤って認識し、過剰に反応してしまう状態を指します (Galli et al. 2008)。
例えるなら、こんな状況です。
街(=あなたの身体)に、無害な観光客(=スギ花粉)がやってきました。それを見た防衛軍(=免疫システム)が、「大変だ!あれは凶悪なテロリストだ!」と勘違い。観光客1人を追い出すために、街全体(=鼻や目)に向けて、催涙ガス(=ヒスタミンなど)を撒き散らし、あちこちで強力な放水を始めるようなものです。
結果どうなるでしょう?
敵と誤認された観光客(花粉)はたしかに居心地が悪いかもしれませんが、それ以上に、街(=あなた自身)が催涙ガスで涙や鼻水が止まらなくなり(=目のかゆみ、鼻水)、放水で大混乱(=鼻づまり)、けたたましいサイレン(=くしゃみ)でパニックになります。場合によっては、道路(=気管支)が煙で通れなくなる(=呼吸困難)ことさえあるのです。
このように、敵(と誤認されたアレルゲン)への攻撃が、結果的に自分自身の身体(鼻の粘膜、皮膚、気管支など)をも激しく傷つけてしまい、不快な症状を引き起こす。これがアレルギーの正体です。
この「免疫システムに勘違いされてしまった、本当は無害な原因物質」のことを、医学用語で「アレルゲン」と呼びます。
アレルギーが起こる2段階のメカニズム(I型アレルギー)
アレルギーにはいくつかのタイプ(I〜IV型など)が知られていますが、私たちが一般的に「アレルギー」と呼ぶものの多く、例えば花粉症、気管支喘息、アトピー性皮膚炎の一部、食物アレルギー、アナフィラキシーショックなどは、「I型(いちがた)アレルギー」、別名「即時型アレルギー」というメカニズムで説明されることがほとんどです。
このI型アレルギーは、症状が出るまでに大きく分けて2つのステップを踏むことが知られています。いきなり起こるわけではない、というのがポイントです。
ステップ1:感作(かんさ)- 防衛システムが「敵」を誤って記憶する
アレルギーは、アレルゲンが初めて体内に入った時にいきなり発症するわけではありません。最初のステップは、免疫システムがそのアレルゲンを「危険な敵」として学習し、攻撃準備を整える「感作(かんさ)」と呼ばれる段階です。
- アレルゲンの侵入と認識:
アレルゲン(例:スギ花粉)が鼻の粘膜などから侵入します。 - 抗原提示と指令:
免疫の司令塔である細胞(ヘルパーT細胞)が、このスギ花粉を「敵」と誤認します。このとき、免疫システムが本来、寄生虫などに対して用いるべき「Th2(ティーエイチツー)型」と呼ばれる防衛戦略のスイッチが誤って入ってしまい (Romagnani 2000)、攻撃部隊であるリンパ球(B細胞)に対して「スギ花粉専用の武器を作れ」という指令を出します。 - IgE抗体の産生:
指令を受けたB細胞は、抗体産生工場である「形質細胞(けいしつさいぼう)」へと分化し、「IgE抗体」と呼ばれる、特定のアレルゲン(この場合はスギ花粉)だけを攻撃対象とする専用の武器(ミサイルのようなもの)を大量に生産し始めます。 - マスト細胞への配備:
生産されたIgE抗体は、血流に乗って全身に運ばれ、皮膚や粘膜(鼻、目、気道、消化管など)に広く存在する「マスト細胞」の表面に結合します。マスト細胞は和名で「肥満細胞」とも呼ばれますが、これは細胞が膨らんだ(肥満した)ように見えたことに由来するだけで、体型の「肥満(Obesity)」とは一切関係ありません。このマスト細胞は、ヒスタミンなどの化学伝達物質が詰まった「火薬庫」のような細胞だとイメージしてください。
この「感作」の段階では、IgE抗体がマスト細胞に配備されるだけで、アレルギー症状はまだ現れません。いわば、ミサイル(IgE抗体)が火薬庫(マスト細胞)にセットされ、いつでも発射できる準備が整った状態、というわけです。この準備が整うまでに、数週間から数年かかると言われています。
ステップ2:惹起(じゃっき)- 記憶した「敵」の再侵入と症状発現
感作が成立した後、再び同じアレルゲン(スギ花粉)が体内に侵入すると、いよいよアレルギー反応が引き起こされます。これを「惹起(じゃっき)」と呼びます。
- アレルゲンの再侵入と結合:
スギ花粉が再び鼻の粘膜に付着します。 - スイッチオン(架橋):
スギ花粉が、マスト細胞の表面にスタンバイしていた「スギ花粉専用IgE抗体」に結合します。このとき、アレルゲンが隣り合う2つのIgE抗体を橋渡しするように結合する(これを架橋(かきょう)と呼びます)ことが、反応開始のスイッチとなります (Galli et al. 2008)。 - 脱顆粒(だつかりゅう):
スイッチが入ったマスト細胞は、内部に溜め込んでいたヒスタミン、ロイコトリエンといった化学伝達物質(アレルギー症状を引き起こす原因物質)を一気に放出します。これを「脱顆粒(だつかりゅう)」と呼びます。火薬庫が爆発したようなイメージです。 - アレルギー症状の発現:
放出されたヒスタミンなどの化学伝達物質が、即座に周囲の組織に作用します。- 神経を刺激する → くしゃみ(異物を排出しようとする反射)、目や鼻のかゆみ
- 血管を広げ、血液成分の漏れ(透過性)を高める → 鼻水(洗い流そうとする)、鼻づまり(粘膜の腫れ)、目の充血、皮膚の赤み・むくみ(蕁麻疹)
- 気管支の筋肉(平滑筋)を収縮させる → 咳、息苦しさ、ゼーゼーする(喘息発作)
この反応はアレルゲンの侵入から数分〜数十分という非常に短時間で起こるため、「即時型」アレルギーと呼ばれるわけです。
なぜアレルギーは増えているのか?-「衛生仮説」の現在地
これほどまでにアレルギー疾患が増加している理由は何でしょうか。
1989年に英国のストラカン博士が提唱した「衛生仮説(Hygiene Hypothesis)」は、アレルギー増加を説明する重要な手がかりとなりました (Strachan 1989)。これは、幼少期に感染症にかかる機会や、細菌・寄生虫などにさらされる機会が減少した(=衛生的になった)結果、免疫システムが「戦う相手」を見失い、本来無害なアレルゲンに対して過剰に反応するようになったのではないか、という説です。
この仮説は、その後の研究でさらに大きく発展・進化しています。もはや「不潔な方が良い」といった単純な話ではありません。
「衛生仮説」から「生物多様性仮説」へ
現在、この仮説は「オールド・フレンズ仮説(Old Friends Hypothesis)」や「生物多様性仮説(Biodiversity Hypothesis)」として再定式化されています (Rook 2023)。
この考え方の核心は、感染症の病原体そのものよりも、ヒトが進化の過程で常に共生してきたはずの「古き良き友人(Old Friends)」、すなわち土壌や自然環境、あるいは母子・家族間で受け継がれてきた多様な常在微生物(マイクロバイオーム)への暴露が、近代的な都市生活や食生活によって不十分になったことにある、というものです。
これらの多様な微生物との接触は、免疫システムが「攻撃すべき敵」と「無視すべき無害なもの」を正しく見分けるための「教育」に不可欠であり、特に過剰な免疫反応にブレーキをかける「制御性T細胞(Treg)」の働きを育む上で重要だと考えられています。都市化によるこの「微生物多様性の喪失」が、免疫の調節不全を招いているというわけです。
増加を加速させる「現代のミスマッチ」
この「免疫の教育不足」という基盤的な問題に加えて、現代特有の複数の要因がアレルギー発症の閾値をさらに押し下げ、問題を複雑にしていると考えられています。
- 環境暴露の変化(気候変動と大気汚染):
近年の気候変動による気温とCO₂濃度の上昇は、花粉の飛散シーズンを長期化させ、花粉の生産量そのものを増加させていることが、米国の研究などで示されています (Zhang et al. 2022)。さらに、PM2.5や窒素酸化物(NO₂)、ディーゼル排気ガスといった大気汚染物質がアレルゲンと同時に暴露されることで、気道の上皮バリアが障害され、アレルギーの「感作(ステップ1)」や症状の悪化がより強く引き起こされることが、2024年や2025年のレビューでも繰り返し確認されています (Burbank et al. 2025)。 - 上皮バリア仮説:
アレルギーは、皮膚や気道、腸管といった「上皮バリア」の障害から始まる、という考え方も非常に重要です。2023年のレビュー (Wright et al. 2023) などでは、現代生活で多用される洗剤や界面活性剤、あるいは微小なプラスチック粒子などが、細胞同士の結合(タイトジャンクション)を物理的・化学的に破壊し、そこからアレルゲンが容易に体内に侵入し、感作を引き起こす可能性が指摘されています。つまり、「清潔」のための行動が、意図せず「バリア機能」を損ねている可能性があり、「バリアを壊さない清潔さ」という新しい視点が求められています。 - 食環境の変化(超加工食品):
乳化剤、保存料、人工甘味料などを多く含む「超加工食品(UPF: Ultra-Processed Foods)」の消費増加と、喘息やアレルギー疾患の有病率との関連を示唆する観察研究が、2024年頃から相次いで報告されています。これらの食品添加物や食生活の変化が、腸内細菌叢のバランスを崩したり、腸管のバリア機能に影響を与えたりすることで、免疫応答を乱すのではないかと懸念されています(ただし、現時点では観察研究が中心であり、明確な因果関係の証明には至っていません)。 - 周産期・乳幼児期の要因:
出生時の産道細菌叢への暴露(経膣分娩か帝王切開か)や、乳幼児期の抗菌薬の使用が、腸内細菌叢の定着パターンを変え、将来のアレルギー発症リスクに影響する可能性も指摘されています。例えば、帝王切開とアレルギーの関連を示すメタ解析 (Liu et al. 2024) や、乳幼児期の抗菌薬使用と喘息の関連を示す研究 (Gold et al. 2024) があります。一方で、日本の大規模コホート研究では帝王切開とアレルギーの関連は明瞭でなかったとする報告 (Tamai et al. 2025) もあり、地域差や他の交絡因子も複雑に関わっているようです。これらの医療行為は医学的な必要性に基づいて行われるものであり、リスクとベネフィットを個別に判断することが大前提です。
要するに、1989年の「衛生仮説」は、2020年代の現在、「①微生物多様性の喪失(免疫の教育不足)」と「②上皮バリアの障害(アレルゲンの侵入促進)」という2つの大きなメカニズムを核として、そこに気候変動、大気汚染、食生活の変化といった現代特有の要因が複合的に作用し、アレルギー疾患を増加させている、という統合的なモデルへと進化しています。
こうした理解は、例えばフィンランドで行われた、都市部の保育園の園庭を生物多様性の高い「森林」の土壌や植生に入れ替える介入試験(Roslund et al. 2020)につながっています。この研究では、介入を受けた子どもたちの皮膚や腸内の微生物多様性が高まり、免疫系の調節マーカーが改善したことが示されました。これは、医療だけでなく、「都市や生活環境をデザインし直す」という新しい予防戦略の可能性を示唆しています。
アレルギーへの基本的な対処戦略
この「I型アレルギー」のメカニズムを理解すると、私たちが取りうる基本的な治療戦略が非常に論理的であることがわかります。
1. アレルゲンの回避(原因の除去)
最も根本的な対策は、「ステップ2」の引き金となるアレルゲン(スギ花粉、ハウスダスト、特定の食物など)を、物理的に体内に入れないことです。原因がわかっていれば、マスクの着用、こまめな清掃、原因食物の除去などが有効な手段となります。
2. 症状の緩和(対症療法)
アレルギー反応が起きてしまった場合、「ステップ2」で放出された化学伝達物質の働きをブロックすることで症状を抑えます。
代表的なのが「抗ヒスタミン薬」です。これは、マスト細胞から放出されたヒスタミンが、神経や血管の「受容体(鍵穴)」に結合するのを先回りして阻害(ブロック)する薬です。これにより、くしゃみ、鼻水、かゆみを抑えます。鼻づまりには、もう一つの原因物質であるロイコトリエンの働きを抑える薬(抗ロイコトリエン薬)が有効な場合があります。
また、「ステロイド点鼻薬・吸入薬」は、アレルギーによる「炎症」そのものを強力に抑え込むことで、症状を根本的に改善する効果が期待されます。
3. 免疫システムの「再教育」(アレルゲン免疫療法)
対症療法が症状を「抑える」治療であるのに対し、免疫システムそのものに働きかけ、アレルギー反応を長期的に抑制し、体質の改善を目指す治療法が「アレルゲン免疫療法」です。
これは、「ステップ1」の「誤認識」を修正する治療法と言えます。原因となるアレルゲン(スギ花粉やダニ)のエキスを、少量から徐々に増やしながら、長期間(通常3〜5年)にわたり投与し続けます。
これにより、免疫システムがそのアレルゲンに徐々に「慣れ」、過剰なIgE抗体を作らなくなったり、逆に反応を抑えるブレーキ役の細胞(制御性T細胞など)が働いたりするよう、免疫システムを「再教育」していきます。これを「免疫寛容(めんえきかんよう)」の誘導と呼びます。
まとめ:メカニズムの理解こそが「知的武装」になる
アレルギーは、単なる「体質」や「運」の問題ではなく、「IgE抗体」や「マスト細胞」、「ヒスタミン」などが関与する、免疫システムの明確なメカニズム(誤認識と過剰反応)によって引き起こされる科学的な現象です。
このメカニズムを理解することで、
- なぜ、初めて花粉を吸った年には発症しないことがあるのか(感作の期間が必要だから)
- なぜ、抗ヒスタミン薬が「かゆみ」や「鼻水」に効くのか(ヒスタミンの働きをブロックするから)
- なぜ、免疫療法は時間がかかり、体質の改善が期待できるのか(免疫システムの「再教育」が必要だから)
といった、治療や対策の「なぜ」が論理的に見えてきます。
ご自身の身体という最も重要な資本を、科学的根拠に基づいて理解すること。それこそが、溢れる健康情報に惑わされず、ご自身にとって最適な選択を行う「健康のCEO」となるための、第一歩であり、最も強力な「知的武装」となると、私たちは信じています。
※本記事は情報提供を目的としたものであり、特定の治療法を推奨するものではありません。健康に関するご懸念やご相談は、必ず専門の医療機関にご相談ください。
参考文献
- Akdis, C. A. (2021). Does the epithelial barrier hypothesis explain the increase in allergy, autoimmunity and other chronic conditions?. Nature Reviews Immunology, 21(11), 739–751.
- Baba, K., Nakagawa, T., Terada, N., Nomura, Y., Ogino, S. & Igarashi, T. (1998). Epidemiological survey of allergic rhinitis in Japan 1998 (JAPOC 1998). Nippon Jibiinkoka Gakkai Kaiho, 101(11), 1229–1236.
- Bloomfield, S. F., Rook, G. A., Scott, E. A., Shanahan, F., Stanwell-Smith, R. & Turner, P. (2016). Time to abandon the hygiene hypothesis: new perspectives on allergic disease, the human microbiome, infectious disease prevention and the role of targeted hygiene. Perspectives in Public Health, 136(4), 213–224.
- Burbank, A. J., Long, Y., Kim, S. J., Kaplan, B. J. & Hernandez, M. L. (2025). Climate change, air pollution, and allergic respiratory diseases: a review of current evidence, mechanistic pathways, and future research needs. Annals of Allergy, Asthma & Immunology, 134(1), 16–25.
- Galli, S. J., Tsai, M. & Piliponsky, A. M. (2008). Mast cells, basophils, and allergy. The New England Journal of Medicine, 358(17), 1809–1817.
- Gold, M., Vuillermin, P., Netting, M. J., Perrett, K. P., Burgner, D. P., Tang, M. L. K., et al. (2024). Antibiotic use in the first year of life and subsequent risk of asthma: a systematic review and meta-analysis. The Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice, 12(3), 718–726.e6.
- Liu, X., Wang, Y., Zhang, X., Li, J., Lin, S., Yang, Z., et al. (2024). Cesarean section delivery and risk of allergic diseases in offspring: an updated systematic review and meta-analysis of cohort studies. The Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice, 12(1), 159–172.e13.
- Okada, H., Kuhn, C., Feillet, H. & Bach, J. F. (2010). The 'hygiene hypothesis' for autoimmune and allergic diseases: an update. Trends in Immunology, 31(4), 149–157.
- Okamoto, Y., Kurono, Y., Shirasaki, H., Horiguchi, S., Fujieda, S., Ota, N., et al. (2020). Nationwide survey on the prevalence of allergic rhinitis and pollinosis (JAPOC2019) in Japan in 2019. Allergology International, 69(2), 223–231.
- Okubo, K., Baba, K., Imai, T., Ohsuna, H., Ohta, K., Ogino, S., et al. (2008). Epidemiological survey of allergic rhinitis in Japan 2008 (JAPOC 2008). Nippon Jibiinkoka Gakkai Kaiho, 111(12), 876–887.
- Romagnani, S. (2000). The role of Th1/Th2 cells in human allergic diseases. Journal of Allergy and Clinical Immunology, 105(2 Pt 2), S399–S408.
- Rook, G. A. W. (2023). The Old Friends Hypothesis: a 2023 update. Current Allergy and Asthma Reports, 23(8), 411–419.
- Roslund, M. I., Puhakka, R., Grönroos, M., Nurminen, N., Oikarinen, S., Gazali, A. M., et al. (2020). Biodiversity intervention enhances immune regulation and health-associated commensal microbiota among daycare children. Science Advances, 6(42), eaba2578.
- Strachan, D. P. (1989). Hay fever, hygiene, and household size. BMJ, 299(6710), 1259–1260.
- Tamai, K., Tsuji, M., Nakahara, S., Kawamoto, T., Nishihara, M., Arima, T., et al. (2024). Cesarean section and risk of allergic diseases in Japanese children: the Japan Environment and Children's Study (JECS). Allergy, 79(11), 3048–3051.
- Wright, B. L., Kotecha, S., Mohammed, S., Afzal, S., Jones, C. J., Akdis, C. A., et al. (2023). The epithelial barrier hypothesis: a review of its role in the pathogenesis of allergic diseases. The Journal of Allergy and Clinical Immunology, 151(1), 33–46.
- Zhang, Y., Steiner, A. L., Posselt, D. J., Lyon, B., Adhikari, A., Anderegg, W. R. L., et al. (2022). Projected climate change impacts on pollen concentrations and season duration in the U.S. Nature Communications, 13(1), 1279.
ご利用規約(免責事項)
当サイト(以下「本サイト」といいます)をご利用になる前に、本ご利用規約(以下「本規約」といいます)をよくお読みください。本サイトを利用された時点で、利用者は本規約の全ての条項に同意したものとみなします。
第1条(目的と情報の性質)
- 本サイトは、医療分野におけるAI技術に関する一般的な情報提供および技術的な学習機会の提供を唯一の目的とします。
- 本サイトで提供されるすべてのコンテンツ(文章、図表、コード、データセットの紹介等を含みますが、これらに限定されません)は、一般的な学習参考用であり、いかなる場合も医学的な助言、診断、治療、またはこれらに準ずる行為(以下「医行為等」といいます)を提供するものではありません。
- 本サイトのコンテンツは、特定の製品、技術、または治療法の有効性、安全性を保証、推奨、または広告・販売促進するものではありません。紹介する技術には研究開発段階のものが含まれており、その臨床応用には、さらなる研究と国内外の規制当局による正式な承認が別途必要です。
- 本サイトは、情報提供を目的としたものであり、特定の治療法を推奨するものではありません。健康に関するご懸念やご相談は、必ず専門の医療機関にご相談ください。
第2条(法令等の遵守)
利用者は、本サイトの利用にあたり、医師法、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)、個人情報の保護に関する法律、医療法、医療広告ガイドライン、その他関連する国内外の全ての法令、条例、規則、および各省庁・学会等が定める最新のガイドライン等を、自らの責任において遵守するものとします。これらの適用判断についても、利用者が自ら関係各所に確認するものとし、本サイトは一切の責任を負いません。
第3条(医療行為における責任)
- 本サイトで紹介するAI技術・手法は、あくまで研究段階の技術的解説であり、実際の臨床現場での診断・治療を代替、補助、または推奨するものでは一切ありません。
- 医行為等に関する最終的な判断、決定、およびそれに伴う一切の責任は、必ず法律上その資格を認められた医療専門家(医師、歯科医師等)が負うものとします。AIによる出力を、資格を有する専門家による独立した検証および判断を経ずに利用することを固く禁じます。
- 本サイトの情報に基づくいかなる行為によって利用者または第三者に損害が生じた場合も、本サイト運営者は一切の責任を負いません。実際の臨床判断に際しては、必ず担当の医療専門家にご相談ください。本サイトの利用によって、利用者と本サイト運営者の間に、医師と患者の関係、またはその他いかなる専門的な関係も成立するものではありません。
第4条(情報の正確性・完全性・有用性)
- 本サイトは、掲載する情報(数値、事例、ソースコード、ライブラリのバージョン等)の正確性、完全性、網羅性、有用性、特定目的への適合性、その他一切の事項について、何ら保証するものではありません。
- 掲載情報は執筆時点のものであり、予告なく変更または削除されることがあります。また、技術の進展、ライブラリの更新等により、情報は古くなる可能性があります。利用者は、必ず自身で公式ドキュメント等の最新情報を確認し、自らの責任で情報を利用するものとします。
第5条(AI生成コンテンツに関する注意事項)
本サイトのコンテンツには、AIによる提案を基に作成された部分が含まれる場合がありますが、公開にあたっては人間による監修・編集を経ています。利用者が生成AI等を用いる際は、ハルシネーション(事実に基づかない情報の生成)やバイアスのリスクが内在することを十分に理解し、その出力を鵜呑みにすることなく、必ず専門家による検証を行うものとします。
第6条(知的財産権)
- 本サイトを構成するすべてのコンテンツに関する著作権、商標権、その他一切の知的財産権は、本サイト運営者または正当な権利を有する第三者に帰属します。
- 本サイトのコンテンツを引用、転載、複製、改変、その他の二次利用を行う場合は、著作権法その他関連法規を遵守し、必ず出典を明記するとともに、権利者の許諾を得るなど、適切な手続きを自らの責任で行うものとします。
第7条(プライバシー・倫理)
本サイトで紹介または言及されるデータセット等を利用する場合、利用者は当該データセットに付随するライセンス条件および研究倫理指針を厳格に遵守し、個人情報の匿名化や同意取得の確認など、適用される法規制に基づき必要とされるすべての措置を、自らの責任において講じるものとします。
第8条(利用環境)
本サイトで紹介するソースコードやライブラリは、執筆時点で特定のバージョンおよび実行環境(OS、ハードウェア、依存パッケージ等)を前提としています。利用者の環境における動作を保証するものではなく、互換性の問題等に起因するいかなる不利益・損害についても、本サイト運営者は責任を負いません。
第9条(免責事項)
- 本サイト運営者は、利用者が本サイトを利用したこと、または利用できなかったことによって生じる一切の損害(直接損害、間接損害、付随的損害、特別損害、懲罰的損害、逸失利益、データの消失、プログラムの毀損等を含みますが、これらに限定されません)について、その原因の如何を問わず、一切の法的責任を負わないものとします。
- 本サイトの利用は、学習および研究目的に限定されるものとし、それ以外の目的での利用はご遠慮ください。
- 本サイトの利用に関連して、利用者と第三者との間で紛争が生じた場合、利用者は自らの費用と責任においてこれを解決するものとし、本サイト運営者に一切の迷惑または損害を与えないものとします。
- 本サイト運営者は、いつでも予告なく本サイトの運営を中断、中止、または内容を変更できるものとし、これによって利用者に生じたいかなる損害についても責任を負いません。
第10条(規約の変更)
本サイト運営者は、必要と判断した場合、利用者の承諾を得ることなく、いつでも本規約を変更することができます。変更後の規約は、本サイト上に掲載された時点で効力を生じるものとし、利用者は変更後の規約に拘束されるものとします。
第11条(準拠法および合意管轄)
本規約の解釈にあたっては、日本法を準拠法とします。本サイトの利用および本規約に関連して生じる一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
For J³, may joy follow you.